チューダーの腕時計を長く愛用するためには、定期的なオーバーホールが欠かせません。
特に「チューダー オーバーホール 載せ替え」と検索される方の多くは、どこに依頼すればよいのか、費用はどれくらいかかるのかといった不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
本記事では、「オーバーホールはどこでできるのか」「正規サービスと民間修理店の料金正規や費用の違い」「10年に一度で十分なのか」など、メンテナンスに関する基本知識をわかりやすく解説していきます。
また、「オーバーホールできない場合の対処法」や、「並行輸入モデルの注意点」、「中古の保証期間は?といった購入後のサポート」についても触れていきます。
さらに、同じく人気の高い「ロレックス」との違いや、「チューダーの時計はなぜ安い」と言われる理由、「チューダーの時計は値上がりしましたか?」という近年の価格動向まで、幅広く網羅しています。
チューダーの時計を安心して使い続けるための情報を、初心者にもわかりやすく丁寧にまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
-
チューダーのオーバーホールを依頼できる場所や選び方
-
載せ替えや修理が必要な場合の対応策
-
正規料金や民間修理との費用差
-
並行輸入や中古購入時の注意点や保証の違い
【チューダー】のオーバーホール載せ替えの基本知識

チューダー公式
-
オーバーホールはどこでできる?
-
チューダーの時計はなぜ安いのか解説
-
中古の保証期間は?購入前に要確認
-
並行輸入モデルの注意点とは?
-
オーバーホールできない場合の対応策
オーバーホールはどこでできる?

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
オーバーホールは、正規サービスセンターや時計修理専門店、さらには一部の街の時計店でも依頼することができます。
まず、もっとも安心できるのは「チューダーの正規サービスセンター」です。ここでは純正部品を使用し、ブランドの基準に則ったメンテナンスが受けられるため、品質や保証面で安心感があります。ただし、その分料金は高めで、納期もやや長くなる傾向があります。
一方、コストを抑えたい場合は「時計修理専門店」や「民間の修理業者」も選択肢に入ります。信頼できる技術者が在籍している店舗であれば、品質面でも十分満足できることが多く、価格や納期の面でも柔軟です。
ただし、店舗によって技術力や対応品質にばらつきがあるため、実績や口コミの確認は欠かせません。
さらに、街中の時計店でもオーバーホールを受け付けているケースがありますが、こちらは受付のみで、実際の作業は外部の修理業者に委託されることがほとんどです。このため、対応内容や価格はお店によって大きく異なります。
いずれにしても、オーバーホールを依頼する際は、「どこで」「誰が」「どのように」作業を行うのかを事前にしっかり確認することが重要です。
信頼できる店舗選びが、チューダーの時計を長く使い続けるための第一歩となります。
チューダーの時計はなぜ安いのか解説

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
チューダーの時計が比較的手の届きやすい価格帯で販売されている理由は、ロレックスと比較した際のブランド戦略や製造工程の違いにあります。
そもそもチューダーは、ロレックスの創業者ハンス・ウイルスドルフが「ロレックスの品質を保ちつつ、より手ごろな価格で提供できる時計を作る」というコンセプトで立ち上げたブランドです。そのため、品質や精度は高水準ながらも、価格を抑える工夫が随所に見られます。
一つの要因として、「ムーブメントの違い」が挙げられます。過去のチューダーは、ETA社製の汎用ムーブメントを採用していたため、製造コストを大きく抑えることができました。現在では自社製ムーブメントも増えていますが、それでもロレックスと比べて製造規模や装飾にかかるコストは抑えられています。
また、外装部品やケース素材にも違いがあります。例えば、チューダーはステンレススチールの使用や、複雑機構の採用を控えることで価格をコントロールしています。見た目は似ていても、微細な部分に差があるのです。
このように、チューダーの時計はコストを抑えながらもデザイン性と機能性を兼ね備えており、「価格以上の価値がある」と多くのユーザーから支持されています。
ロレックスの弟分としての立ち位置を活かした価格戦略が、今もなお魅力の一つとなっています。
中古の保証期間は?購入前に要確認

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
中古のチューダー時計を購入する際、保証期間がどれくらいあるのかを確認することはとても重要です。
これは、購入後に不具合が起きた際、修理対応をスムーズに行うために欠かせない情報だからです。
まず理解しておきたいのは、「メーカー保証」と「販売店独自の保証」があるという点です。新品購入時に付いてくるメーカー保証は、通常2年から5年程度ですが、中古品の場合はその残り期間しか利用できません。
さらに、保証書がなければ、メーカー保証自体が無効になるケースもあるため注意が必要です。
一方で、販売店による保証は店舗ごとに条件が異なります。例えば、3か月や6か月の保証を付ける店もあれば、1年の長期保証を提供しているところもあります。ただし、保証の範囲には制限がある場合が多く、外装のキズや経年劣化は対象外とされることが一般的です。
このため、中古時計を購入する前には「保証の有無・内容・期間」を必ず確認し、できるだけ保証が充実している店舗を選ぶことが安心につながります。
購入後のトラブルを避けるためにも、このポイントを軽視しないようにしましょう。
並行輸入モデルの注意点とは?

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
オーバーホールできない場合の対応策
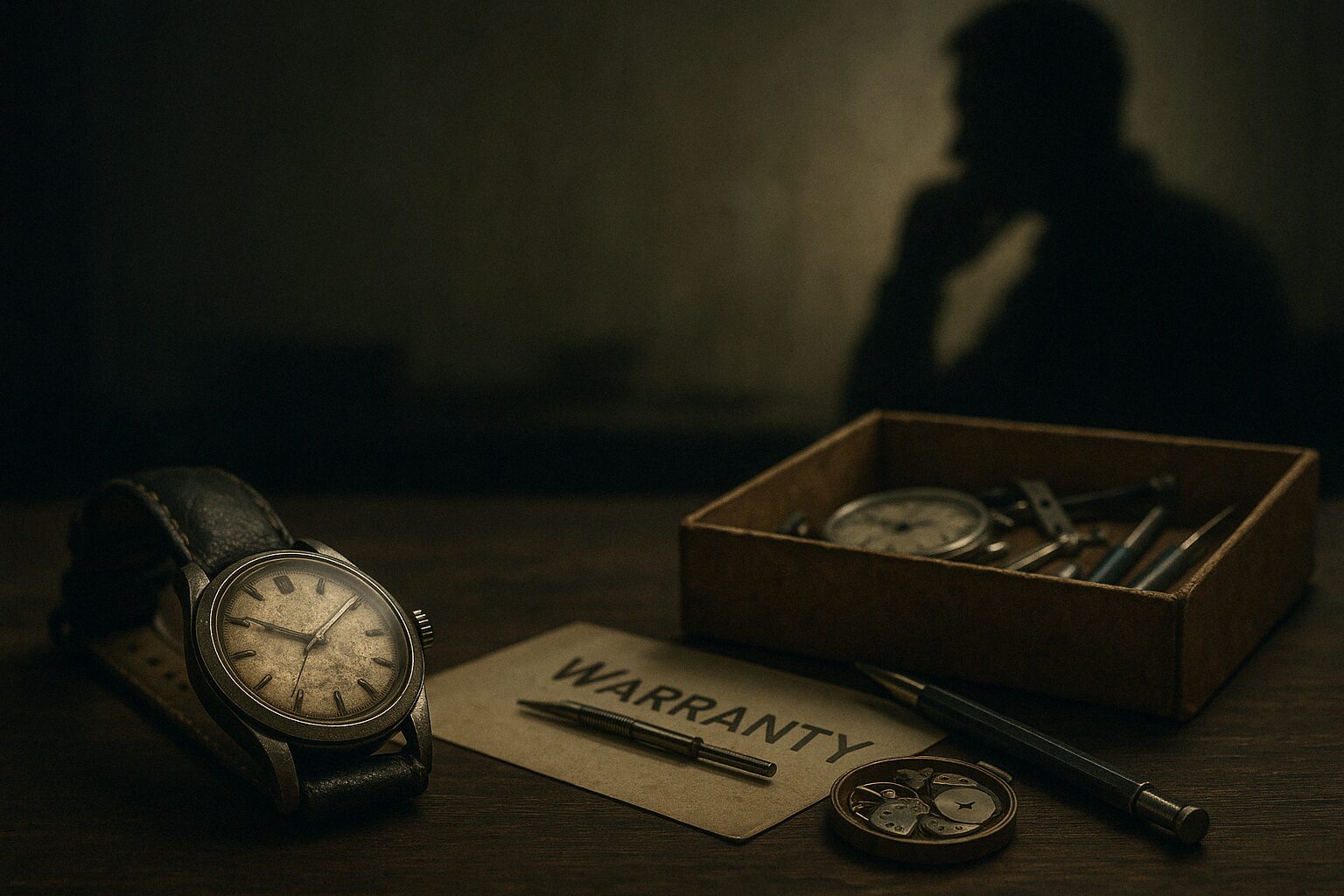
LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
チューダーの時計がオーバーホールできないと言われた場合、いくつかの対応策を知っておくと安心です。
主に、製造終了モデルやパーツ供給が難しいモデルに多く見られるケースです。
まず第一に検討したいのが、「修理専門の時計店に依頼する」という方法です。メーカーでは対応できない場合でも、技術力のある民間の時計修理店では、代替パーツを使って対応可能なことがあります。こうした店舗は全国に点在しており、中にはチューダーをはじめとする高級時計専門の修理業者も存在します。
次に、パーツ取り用として同型の中古モデルを探すという選択肢もあります。使えなくなったパーツをそちらから移植することで、再び時計が使えるようになるケースもあるため、時計好きの間ではよく知られている手法です。
ただし、こうした方法は全体的なコストが高くなる可能性がありますし、完全なオリジナル状態ではなくなる点にも注意が必要です。また、正規保証は適用外となるため、価値や将来的な売却を考えている人にとってはデメリットとなることもあります。
どうしても修理が難しい場合は、下取りに出して新しいモデルを購入するのも一つの手です。
査定額はモデルや状態によって異なりますが、下取りを活用すれば次の購入費用の一部に充てることができます。
【チューダー】のオーバーホール載せ替えの費用事情

チューダー公式
-
オーバーホールの料金正規とその費用感
-
ロレックスと比較したときの違いは?
-
チューダーの時計は値上がりしましたか?
-
オーバーホールは10年に1度でいいのか?
-
費用対効果を考えたメンテナンスのタイミング
オーバーホールの料金正規とその費用感

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
チューダーの時計を正規サービスでオーバーホールする場合、気になるのはやはりその費用感です。
価格だけでなく、サービスの内容や信頼性も含めて比較することが大切です。
基本的に、正規のオーバーホール料金はモデルによって異なります。例えば、シンプルな自動巻きモデルであれば3万円台後半から5万円程度、クロノグラフなどの複雑機構を備えたモデルになると、7万円以上かかるケースも珍しくありません。
この費用には、ムーブメントの分解・洗浄・注油・調整といった作業のほか、パッキンの交換や防水検査なども含まれています。正規サービスセンターで対応する場合は、すべて純正パーツが使用され、作業後には1年〜2年の保証が付くのが一般的です。
一方、民間の修理店では費用が抑えられることが多く、場合によっては半額近い価格でオーバーホールできることもあります。ただし、純正パーツの使用有無や作業の品質には差があるため、信頼できる店舗かどうかをしっかり見極める必要があります。
費用だけで判断するのではなく、「どこまで安心して任せられるか」を重視することが、長く時計を愛用するためのポイントです。
ロレックスと比較したときの違いは?

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
ロレックスとチューダーは、時計愛好家の間でしばしば比較される存在です。
それもそのはず、どちらもロレックス創業者であるハンス・ウイルスドルフによって設立されたブランドであり、技術や品質に関して多くの共通点があります。
しかし、その立ち位置や細部においては明確な違いが存在します。ここでは、価格、素材、ムーブメント、デザインという観点から両者の違いを詳しく見ていきます。
まず注目したいのは、価格帯とブランドイメージの違いです。ロレックスは高級時計の代名詞とも言える存在であり、その価格は数十万円から数百万円に及ぶものもあります。その背景には、緻密な設計と高級素材の使用、そしてブランドとしての歴史と信頼があります。
一方で、チューダーは「ロレックスの技術を活かしながら、より手の届きやすい価格で高品質な時計を提供する」という目的のもとに生まれたブランドです。
価格帯はロレックスよりも抑えられており、若年層や初めて機械式時計を購入するユーザーにとっても手が届きやすい存在となっています。高級感よりも実用性とコストパフォーマンスを重視する人に適した選択肢と言えるでしょう。
素材に関しても明確な違いがあります。ロレックスでは、耐食性や強度、光沢に優れた904Lステンレススチール(通称:オイスタースチール)を使用しているのに対し、チューダーは316Lステンレススチールを採用しています。
316Lも高品質な素材であり、日常使いには十分な性能を持っていますが、904Lはより高級な素材として差別化されています。こうした素材選びも、両者の価格帯の違いに反映されています。
ムーブメントの違いも見逃せません。かつてのチューダーはETA社の汎用ムーブメントを搭載していましたが、近年では自社製ムーブメントの開発・採用が進められており、精度や耐久性は大きく向上しています。
ロレックスももちろん自社製ムーブメントを採用しており、クロノメーター認定を受けた高精度のものばかりです。ただし、細部の仕上げやパーツの品質においては、ロレックスの方がより高水準であることは否めません。これは、価格差を裏付ける要因のひとつとも言えるでしょう。
デザイン面での特徴も対照的です。ロレックスは伝統を重んじるデザインが中心であり、モデルチェンジも慎重に行われるため、どの年代のモデルも統一感があります。そのため、フォーマルなシーンにも違和感なく溶け込みます。
一方、チューダーはより自由なデザイン哲学を持ち、ヴィンテージテイストやカジュアルなスタイルを積極的に取り入れています。「ブラックベイ」シリーズに代表されるように、カラーバリエーションやストラップの選択肢が豊富で、個性を出しやすい点が魅力です。
このように、ロレックスとチューダーは「兄弟ブランド」としての共通点を持ちながらも、異なる方向性で発展してきた存在です。ロレックスはブランド価値や資産性、高級感を重視したい人に向いていますが、チューダーは価格以上の性能や、デザインの幅広さを楽しみたい人におすすめです。
どちらが優れているかではなく、自分の使い方や目的に合わせて選ぶことが、満足度の高い時計選びにつながります。
チューダーの時計は値上がりしましたか?

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
ここ数年で、チューダーの時計は確かに値上がりを続けています。
これは一時的な動きではなく、ブランドとしての方向性や外部環境の影響を受けた、継続的な価格改定の流れと見ることができます。
実際にモデルによっては、わずか数年で数万円から十万円近く価格が上昇しているケースもあり、以前よりも「手の届きやすい高級時計」というイメージに変化が見られます。
この値上がりの背景には、いくつかの要因があります。まず、原材料費の上昇です。高級時計に使われるステンレススチールやサファイアクリスタルといった素材は、国際情勢や需給バランスの影響を受けやすく、近年は特に価格が高騰しています。
また、貴金属を使用しているモデルや、クロノグラフのような複雑機構を備えたモデルにおいては、その傾向がより顕著です。
次に、製造・開発コストの増加も無視できません。近年のチューダーは、ETAムーブメントから自社製ムーブメントへの移行を進めていますが、自社ムーブメントの開発には大きな投資が必要です。
これに加え、品質管理体制の強化やアフターサービスの充実も進められており、製品全体の完成度を高めるための取り組みがコストに反映されています。これらの積極的な改善は、ユーザーにとって価値ある変化である反面、販売価格にも影響を及ぼす結果となっています。
さらに、為替相場の変動も価格改定の一因となっています。特にスイスフランと日本円の為替差は、輸入品であるスイス時計全体にとって重要な要素です。円安が進行するほど、日本国内での販売価格は上昇しやすくなるため、チューダーもその影響を受けていると考えられます。
2023年には2度の価格改定が行われ、具体的には1月と9月にそれぞれ実施されました。ステンレススチール製のベーシックなモデルでは平均で約8%の上昇、金属とステンレスを組み合わせたコンビモデルでは最大11%近くの値上がりが見られました。
人気の「ブラックベイ」シリーズを例に挙げれば、改定前と比べて数万円以上高くなっているモデルもあり、過去に比べると購入時のハードルが確実に上がっています。
このような価格上昇は、購入を検討している消費者にとって少なからず影響を与えます。たとえば、同じ予算で購入できたはずのモデルが手の届かない存在になったり、初めての機械式時計として検討していた人が別のブランドに目を向けるケースもあるでしょう。
しかし、その一方で、チューダーは依然として「価格に見合った価値がある」と評価されています。ロレックス譲りの信頼性、自社ムーブメントの進化、ヴィンテージ感と現代性を両立させたデザインなど、他ブランドにはない魅力が凝縮されています。
今後も価格改定の動きは続く可能性があります。だからこそ、購入を考えている方は、単に「安いから買う」「値上がる前に買う」という視点だけでなく、時計としての価値や将来的なメンテナンスコストまで含めて検討することが大切です。
購入のタイミングを見極めるには、信頼できる正規販売店や並行輸入業者から最新の価格動向や在庫状況を聞くことも有効です。
最終的に、チューダーの時計は価格が上昇している今でも、性能・デザイン・ブランド価値のバランスが取れた、コストパフォーマンスに優れた選択肢であることに変わりありません。
慎重に情報を集め、予算と希望に合う1本を見つけることが、満足度の高い買い物につながります。
オーバーホールの際にムーブメントを交換する場合、チューダーではリコンディションドムーブメント(再生ムーブメント)を使用することがあります。これは、オーバーホールで回収したムーブメントをスイスで調整し、再利用するもので、品質と信頼性を確保しつつ、コストを抑えるための手法です。 (参考:tudorwatch)
オーバーホールは10年に1度でいいのか?

LUXURY WORLD WATCHES:イメージ
チューダーの時計に限らず、機械式時計は定期的なオーバーホールが必要です。
「10年に1度でも大丈夫」といった意見も見かけますが、実際には使用状況によって適切なタイミングは異なります。
まず、毎日使用している時計であれば、内部のオイル劣化やパーツの摩耗が進行しやすいため、5〜7年に一度のオーバーホールが推奨されます。逆に、たまにしか使わない場合でもオイルは自然と乾くため、やはり定期的なメンテナンスは欠かせません。
10年近くメンテナンスをせずに放置すると、ムーブメント内部に負荷がかかり、通常よりも修理費が高額になる可能性があります。これは、オーバーホールでは済まず、パーツ交換が必要になるケースがあるためです。
さらに、メーカー保証の条件には「定期的なメンテナンスを受けていること」が含まれることも多く、過度な放置は保証対象外になるリスクもあります。
このように考えると、「10年に1度」という感覚は少し楽観的すぎるかもしれません。
時計の状態を良好に保ち、将来的なコストを抑えるためにも、適切なタイミングでのオーバーホールを意識することが大切です。
費用対効果を考えたメンテナンスのタイミング
オーバーホールは安価な作業ではないため、費用対効果を意識したタイミングで行うことが重要です。
必要以上に頻繁に行うと出費がかさみますし、逆に放置すれば修理費用が増す可能性があります。
例えば、チューダーの機械式時計では、正規のオーバーホール費用が約4万〜6万円前後です。数年に一度の支出であれば許容できる範囲ですが、これを毎年行うのは明らかに非効率です。
理想的なタイミングとしては、使用頻度や保管状況によって5〜8年を目安にするのが妥当です。湿気が多い場所に保管している場合や、水に触れる機会が多いモデル(ダイバーズウォッチなど)は、やや短めのスパンでのメンテナンスを検討すると良いでしょう。
また、メンテナンス時には「定期点検」のみを依頼して状態確認だけを行い、必要があればオーバーホールに進むという段階的な方法も有効です。これにより無駄な支出を避けつつ、時計を良好な状態に保つことができます。
結果として、メンテナンスのタイミングは「期間」よりも「状態」を見て判断することが、費用対効果を高めるポイントになります。
日頃からの観察と、信頼できる修理店での定期チェックを組み合わせることが賢明です。
【チューダー】のオーバーホール載せ替えをまとめて解説
- オーバーホールは正規店・修理専門店・街の時計店で依頼可能
- 正規サービスは純正部品使用で信頼性が高い
- 民間修理店は費用が安く納期も柔軟なことが多い
- 店舗選びでは技術力と口コミの確認が重要
- 並行輸入品は正規サポートを受けられない場合がある
- 並行輸入は保証や品質にリスクがあるため慎重な選定が必要
- 中古時計の保証はメーカー保証と販売店保証がある
- 保証の残存期間と内容を購入前に必ず確認する
- チューダーはムーブメントや素材の違いで価格を抑えている
- ロレックスよりもカジュアルでスポーティなモデル展開が多い
- 自社ムーブメント搭載により精度と信頼性が向上している
- 値上がり傾向にあるが依然としてコストパフォーマンスは高い
- オーバーホールできない場合は民間店やパーツ移植で対応可
- メンテナンスは5〜8年周期が望ましく10年放置は避けるべき
- 状態を見てオーバーホールの必要性を判断するのが費用対効果に優れる



